股関節を曲げたときに、前方が「つまる」ような違和感を感じたことはありませんか?
特に大腿骨寛骨臼インピンジメント(FAI:Femoroacetabular Impingement)をはじめとする股関節周辺のトラブルでは、屈曲動作で前方に痛みやつまり感を訴えるケースが少なくありません。
しかもこの症状は、日常生活での動作に支障をきたすだけでなく、スポーツパフォーマンスにも大きな影響を与えます。
本記事では、前方つまり感の代表的な原因をわかりやすく解説するとともに、ご自宅でできるセルフケアから専門的なアプローチまで、改善方法を体系的にまとめました。
ぜひ最後までお読みいただき、つらい違和感の根本解決にお役立てください。
股関節屈曲を構成する関節
- 臼蓋大腿関節:屈曲
- 仙腸関節:ニューテーション(仙骨に対する寛骨の後傾)
- 腰椎椎間関節:屈曲
前方つまり感の原因
1. 骨盤後傾、腰椎屈曲制限
- 脊柱起立筋・腰背筋膜のtightness
- これらが硬くなると骨盤が前傾しやすくなり、腰椎の後弯が減少。
股関節屈曲時に骨盤が十分に後傾できず、「前方がつまる」感じを生む。
- これらが硬くなると骨盤が前傾しやすくなり、腰椎の後弯が減少。
- 寛骨後傾可動性低下(仙結節靱帯・仙棘靱帯のtightness)
- 影響:仙腸関節可動性が不十分になることで、寛骨後傾が制限され、股関節屈曲時につまり感が起こりやすくなる。
2. 大殿筋・中殿筋・深層外旋筋群のtightness
- 大殿筋のtightness
- 大腿骨頭~大転子後方を覆う大殿筋が硬くなると、骨頭後方のスペースが狭まり、屈曲時に骨頭前方偏位を生じやすい。
- 中殿筋(後部線維)のtightness
- 中殿筋は大転子に付着するが、骨頭の後方も覆うため、硬くなると屈曲時に骨頭前方偏位を生じやすくなる。
- 深層外旋筋群(梨状筋含む)のtightness
- 梨状筋、上・下双子筋、大腿方形筋、外閉鎖筋、内閉鎖筋は全て、骨頭や大転子の後方すべりを阻害する・
そのため、屈曲+内旋でさらに圧迫が強まり、「つまる」感覚が顕著に。
- 梨状筋、上・下双子筋、大腿方形筋、外閉鎖筋、内閉鎖筋は全て、骨頭や大転子の後方すべりを阻害する・
3. 前方・上外方偏位による構造的要因
- 骨頭前方位・上外方偏位
- 影響:大腿骨頭が前上方に位置すると、屈曲で臼蓋とのクリアランスが狭まり、早期にインピンジ(衝突)を起こしやすくなる。
- 大腿筋膜張筋tightness
- 影響:腸脛靱帯を介して骨頭を前上方に引き上げる力が強く働き、偏位を助長。屈曲でさらに「つまる」感覚が増す。
4. 関節内インピンジメント
- 腸腰筋インピンジメント
- 影響:腸腰筋腱が大腿骨小転子部〜骨盤前面で関節唇や骨縁に挟まることで、前方つまり感や痛みを生じる。
前方つまり感の改善方法
セルフエクササイズ
・ワイドスプリットスクワット:仙腸関節ニューテーションを起こしたい方を前にして台の上に乗せ、スプリットスクワット
・腰背筋膜のストレッチ:大殿筋+広背筋ストレッチ
・外旋筋群のストレッチ:足を前後に開いて、前足は外旋位で前屈
膝を立てて足を乗せる大殿筋ストレッチ、外旋位で内転する中殿筋ストレッチ
手を後ろに着いて股関節内旋ストレッチ
・大腿筋膜張筋の自原抑制
①長座位、左股関節開排、右足伸展、右足の外側にフォームローラーを縦において、これをまたぐように右股関節屈曲、外転、内旋⇒戻す
*体幹側屈しないようにする。最初は手をついてもok
②長座位、左股関節開排、右股関節内旋から、左脚を浮かしながら左股関節を内旋(膝を立てる)
*手は浮かせる
③長座位、左股関節内旋、右膝立てた状態から、体幹を左右に回旋、側屈する
*回旋の時は両手を前で、側屈の時は後方部で手を組む
④長座位、右股関節屈曲内旋、左股関節開排から、前屈して肘を前におく⇒右股関節を内旋して足を浮かせる、そこからさらに膝も浮かせる
徒手療法
・仙腸関節のニューテーション誘導:仙結節靱帯や仙棘靱帯、後仙腸靱帯の上部線維リリース(これらはニューテーションにより伸長するため)
・iliocapsularisのリリース:関節包に連続性のある腸骨筋やiliocapsularisのリリースでインピンジメントが改善する可能性
・腸腰筋の収縮:iliocapsularisは下前腸骨棘の内下方に起始し、関節包に連続性を持つ。この筋の収縮によって関節包を引っ張り出し、関節包のインピンジメントが改善される可能性
・大腿直筋下のリリース:iliocapsuralis外側の大腿直筋は脂肪体を介して関節包に付着する
・腰方形筋、多裂筋、腸肋筋リリース
・大腿筋膜張筋のリリース:骨頭外上方偏位の改善
・広背筋リリース
各項目の評価方法
・FADIR(屈曲+内転+内旋)で痛みが出るか
⇒痛みが出る場合、屈曲+外転+外旋で痛みが出るかどうか
⇒疼痛が改善する場合、FAIの可能性が高い
⇒疼痛が改善しない場合、関節外インピンジメントの可能性が高い
⇒大腿直筋腱の圧痛を確認する
・FAIの可能性が高い場合、屈曲時に同側の骨盤が後方に引けてくるかどうか確認
⇒例:右股関節屈曲時に骨盤が左回旋すると、相対的に内転内旋位を取りやすい
⇒後方に引けてくる場合、体幹の回旋可動性を確認
・股関節90°屈曲位での外旋可動性を確認
⇒可動性低下がある場合、小殿筋や中殿筋前部線維のtightnessがある可能性
・骨盤後傾可動性:PLFテスト、PMテスト、cat & dog
・PMテスト:膝を立てた背臥位で腸骨稜最頂部とASISの距離を触診して確認し、股関節を他動的に屈曲する。開始肢位から腸骨稜最頂部とASISの距離が1/2以下になれば陰性。基本的には左右差で比較。
・外旋筋群のtightness:FADIR、FADER、腹臥位でHip内旋
・骨頭アライメント:背臥位で大腿骨頭を触診し、前方偏位を確認。大転子を触診し、上方偏位を触診。
・肩屈曲ROM
まとめ
本記事では、股関節屈曲時の「前方つまり感」について、以下4つの視点から原因と改善法を解説しました。
- 骨盤・腰椎域の後方制限
- 大殿筋・中殿筋後部・深層外旋筋群のtightness
- 前方・上外方偏位など構造的要因
- 関節内インピンジメント
それぞれの原因に対して、
- ご自宅で実践できるセルフエクササイズ(ストレッチ・筋膜リリース)
- 専門家による徒手療法(関節モビライゼーション・筋スパズム解除)
- 精度の高い評価法(可動域測定・骨頭アライメントチェック・インピンジテスト)
を組み合わせることで、安全かつ効果的に症状の緩和が期待できます。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の診断・治療を保証するものではありません。症状が強い・長引く場合や不安がある場合は、必ず整形外科や理学療法士などの専門医療機関にご相談ください。

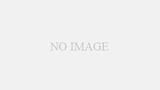
コメント